魔笛
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
W. A. モーツァルト:魔笛
上演時間:約3時間
あらすじ
時と場所:時代不詳のエジプト(正確には、漠然と「ラムセスの時代」と書かれている)
第1幕
日本の狩衣を着た[2]王子タミーノが大蛇(初演前の原案ではライオン)に襲われ、「神々よ助けて!」と叫ぶ。そこに3人の侍女があらわれ彼を救出する。3人はタミーノのことを夜の女王に報告に行くが、そこへ鳥を女王に献上して暮らす鳥刺しのパパゲーノがやってくる。大蛇(ライオン)のことを聞かれ、成り行きから自分でやっつけたとパパゲーノは嘘をつくが、戻ってきた3人の侍女に見つかり口に鍵をかけられてしまう。侍女たちがタミーノに女王の娘パミーナの絵姿を見せると彼は彼女に一目惚れする。そこに夜の女王が登場し、悪魔ザラストロにさらわれて娘を失った悲しみを語り、彼に救出を依頼し、タミーノは意気込んで引き受け、ようやくしゃべることを許されたパパゲーノとともに姫の救出に向かう。2人にはお供の3人の童子が付き添い、タミーノには魔法の笛(魔笛)、パパゲーノには魔法の鈴が渡される。
ザラストロの神殿内。逃げ出そうとしたパミーナを捕らえようとする奴隷頭モノスタトスと部下の奴隷の前に、偵察に来たパパゲーノが突然現れる。彼らは互いに初めて見る姿に驚き、双方ともパミーナを置き去りにして逃げ出す。しかしパパゲーノはすぐに引き返し、パミーナに救出にきたことを告げる。
ザラストロの神殿前にタミーノが案内役の童子につれられてやってくる。3つの扉を順に試すと、最後の扉が開いて弁者(神官の一人)が登場する。2人の長い問答が始まり、ザラストロは悪人ではなく夜の女王のほうが悪人であると告げ、タミーノらは夜の女王達の甘言に引っかかったことに気づく。一人になったタミーノが笛を吹くと、神殿から逃げようとしていたパパゲーノとパミーナが聞きつけやってくる。そこにモノスタトスが登場し、2人を捕らえるが、パパゲーノの鳴らす魔法の鈴の音に動物たちも、奴隷たちも皆浮かれて踊ってどこかに去ってしまう。そこへザラストロと神官たちが登場する。彼は逃げようとしたパミーナにやさしく語り掛けるが、そこにモノスタトスがタミーノを捕らえてやってくる。初対面にもかかわらず、パミーナとタミーノは互いに惹かれて走り寄り、抱き合う。怒ったモノスタトスが2人を引き離すが、ザラストロに足を77回叩きの仕置きを受ける。一同ザラストロの裁きを受け容れて讃える合唱で幕となる。
第2幕
ザラストロは神殿で神官たちにタミーノに試練の儀式を受けさせることを説明し、賛同を得る。一同イシス神とオシリス神を称える。
神官がタミーノとパパゲーノのもとへやってきて、試練について説明する。試練に挑むというタミーノとは対照的に、パパゲーノはそんな面倒なことは御免こうむるという。神官はパパゲーノに試練に打ち勝ったら似合いの娘を世話するといい、ようやくパパゲーノはその気になる。
そこに3人の侍女がやってくる。彼女たちはタミーノがザラストロの言うなりになっているのに驚き、翻意させようとするがタミーノは取り合わない。一方パパゲーノは侍女たちの話に釣られそうになるが、そこに雷鳴とともに神官が現れ彼女らは去る。
場面が変わり、庭でパミーナが眠っている。そこにモノスタトスがやってきてパミーナを我が物にしたいと狂わしい思いを歌うが、そこに夜の女王が登場し、彼は隠れる。女王は復讐の思いを強烈に歌い、パミーナに剣を渡しこれでザラストロを刺すように命じて去る。
隠れていたモノスタトスが出てきてパミーナに迫るが、ザラストロが登場し、彼を叱責して去らせる。モノスタトスは今後は夜の女王に寝返るか、とつぶやく。
パミーナが母の命令のことを話すと、ザラストロは「この神聖な殿堂には復讐などない」、と教団の理想を歌い上げる。
場面転換。2人の神官がタミーノとパパゲーノに沈黙の修行を課して去る。しかしパパゲーノは黙っていることができず、しきりに喋ってはタミーノに制止される。そこへ黒いフードで顔を隠した老女がやってくる。彼女に歳を尋ねると自分は18歳だと言うので、パパゲーノは涙を流して大笑いする。そんなに若いなら彼女には年頃の恋人がいるはずだと思い、パパゲーノが聞いてみると案の定、恋人はいるという。しかもその名はパパゲーノだというので驚いてお前は誰だ?と尋ねる、それと同時に雷鳴が轟き、名前を告げずして彼女はどこかに消えてしまった。
そこへ3人の童子が登場し、2人を励まし酒や食べ物を差し入れる。パパゲーノが喜んで飲み食いしていると、パミーナが現れる。彼女はタミーノを見つけて喜び話しかけるが彼は修行中なので口を利かない。パパゲーノもまた口いっぱいに頬張っているので喋れない(自省して喋れないとする演出もある)。相手にしてもらえないパミーナは、もう自分が愛想をつかされたと勘違いし、大変悲しんでその場を去る。
次の場面で、神官たちとともにザラストロが登場し、タミーノに新たな試練を課すと告げる。パミーナも出てきて試練を受けに出発するタミーノと互いに別れを告げる。
沈黙の業に落第したパパゲーノが神殿に近寄れずうろついていると、神官がやってきて、お前の望みは何かと尋ねる。パパゲーノは恋人か女房がいればいいのに、というと先程の老女がやってきて、私と一緒になると誓わないと地獄に落ちると脅かす。パパゲーノがとりあえず一緒になると約束すると、老女は若い娘に変身する。「パパゲーナ!」と呼びかけ、パパゲーノは彼女に抱擁をしようとするが、神官がパパゲーノにはまだ早いと彼女を連れ去る。
場面が変る。パミーナはタミーノに捨てられたと思い込み、母のくれた剣で自殺しようとしている。3人の童子が現れてそれを止め、彼女をタミーノのもとに連れて行く。タミーノが試練に立ち向かっているところにパミーナが合流し、魔法の笛を使って火と水の試練を通過する。
さらに場面が変り、パパゲーナを失ったパパゲーノが絶望して首を吊ろうとしている。そこに再び童子たちが登場して魔法の鈴を使うように勧める。パパゲーノが鈴を振ると不思議なことにパパゲーナがあらわれ、2人は喜んで子どもを大勢作るんだ、とおおはしゃぎする。
場面が変り、夜の女王と侍女たちを案内してモノスタトスが神殿を襲撃しようとやってくる。しかし光に打ち勝つことはできない。
ザラストロが太陽を讃え、一同イシスとオシリスを讃える合唱のうちにタミーノとパミーナを祝福して幕となる。
プログラムとキャスト
指揮者:イヴァン・フィッシャー
フランツ=ヨーゼフ・ゼリヒ | サラストロ
ジュリアン・プレガルディアン | タミーノ
アリナ・ヴンダーリン | 夜の女王
サマンサ・ガウル | パミーナ
ミレッラ・ハーゲン | 第一の女声
オリビア・フェルミューレン | 第二の女声
マリー・ザイドラー | 第三の女声
マルクス・ヴェルバ | パパゲーノ
サラ・マリア・サン | パパゲーナ
ピーター・ハーヴィー | 語り手 / 第二の神官 / 第二の武装男
ブダペスト・フェスティバル管弦楽団
テアトロ・オリンピコ・ヴィチェンツァ
テアトロ・オリンピコはヴィチェンツァの芸術的な驚異の一つです。ルネサンス期、劇場は後にそうなるような独立した建物ではなく、屋外空間や既存の建物を一時的に整えたものでした。ヴィチェンツァでは、これらの空間は宮殿の中庭やパラッツォ・デッラ・ラジョーネの大広間でした。
1580年、72歳の時、パッラーディオは自ら所属していた文化団体アッカデミア・オリンピカから恒久的な劇場の設計を依頼されました。設計は明らかにローマ劇場に触発されており、ウィトルウィウスの記述通りです:楕円形の段状観客席が列柱に囲まれ、フリーズの上には彫像が配されています。その前には長方形の舞台と、二層の建築秩序をもつ壮麗なプロセニウムがあり、三つのアーケードで開かれ、内部は半柱で区切られ、その中にはアエディキュールや彫像や浮彫パネルを備えたニッチがあります。
批評家は、この作品を「マニエリスム的」と呼びます。光と影の強烈な効果によって、さらに建築家の経験に基づくさまざまな光学的手法が加わり、前面の高さの段階的な縮小が突出した彫像で視覚的に補われ、張り出しやニッチを駆使して奥行き感を増しています。
パッラーディオの設計は彼の死の数か月前に行われ、完成を見ることはありませんでした。息子のシッラが工事を監督し、1583年に劇場を市に引き渡しました。1585年のカーニバルでの初演は記憶に残るものでした。題材はソフォクレスのギリシャ悲劇『オイディプス王』で、舞台装置はテーベの街の七つの通りを、プロセニウムの五つの開口部を通して巧みな遠近法で再現しています。この小さな奇跡の創造者はヴィンチェンツォ・スカモッツィです。その効果はあまりに印象的で、木製構造が劇場の恒久的な一部となりました。スカモッツィは付属スペースも作るよう依頼されました。「オデオ」、アッカデミアの会合が行われたホール、およびヴィチェンツァの画家フランチェスコ・マッフェイによる単色パネルで装飾された「アンティオデオ」です。
新劇場の名声はまずヴェネツィアに広まり、その後イタリア全土に広がり、人文主義の夢である古典芸術の復活が現実となるのを見たすべての人々の称賛を呼び起こしました。その後、順調なスタートにもかかわらず、反宗教改革下の検閲により劇場の活動は中断され、単なる上演の場となりました。1782年にはピウス6世が、1816年にはオーストリア皇帝フランツ1世と1838年にはその後継者フェルディナント1世がここを訪れました。
19世紀半ばには時折クラシック作品が上演されましたが、第二次世界大戦後、爆撃の脅威がなくなった後に再開され、世界に類を見ない劇場としての活動が続きました。
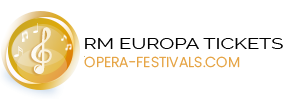
 JP
JP EN
EN DE
DE IT
IT FR
FR ES
ES RU
RU RO
RO
 座席表
座席表 